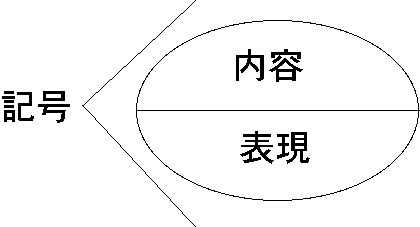
01・“人にとっての情報”おさらい
02・情報と記号学
03・記号学の基本概念
04・記号学から見た“読むこと”と“表すこと”
05・記号学の提示する世界観
06・記号学の考察対象
07・記号学的発想から見た日常世界の情報
08・情報教育に記号学を取り込む意義
・情報教育における“情報”の捉え方の問題
・“情報”の指し示すところ
・情報教育に関する議論においては、(やや?)1の側から2,3,4を捉える発想が強調される
・2,3,4を対象として捉え、掘り下げる発想も必要
・Information、Knowledge、Intelligenceといったものは、「物事の意味」と深い関連がある
・「意味」は「表現」と密接に関連する
・記号学は「意味と表現」とを考える学問
→ 人間の認識のありよう(認識論)と、認識によって捉えられる物事のありよう(存在論)に結びつく
→ 実証科学(経験科学)としての認知科学と密接に関連する
・記号学は“人にとっての情報”を議論するための一つの土台を提供する
・ここでいう記号学とは、F・ソシュール、丸山圭三郎の流れを汲む“フランス系”記号学
・記号・・・“何かを意味する何か”(菅野・1999)
→ 日常を構成するあらゆるものが記号でありうる
→ 例えば、あなたの目の前に立つ“私”も記号である
→ 人間は記号(すなわち意味)に囲まれて生活する。片時もそこを離れることはできない
・記号は、“意味(内容)”と“表現”の二つの側面を持つ
→ “意味(内容)”と“表現”は常に不即不離の関係にある
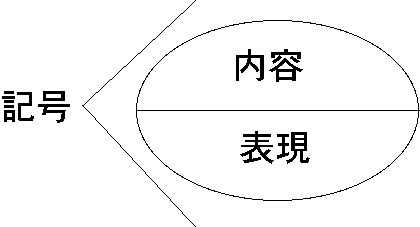
・以下の発想との違いが重要
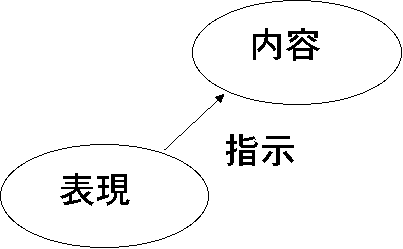
・認識されるのは常に記号そのもの
→ “意味(内容)”と“表現”との区別は、事後的な分析によってはじめて見いだされる
・“内容”と“表現”との結びつきに必然性はない
→ それらの結びつきは、文化的な約束事(コード)によってのみ保証される(恣意性の原理1)
→ 例えば<犬(内容)>を「イヌ(表現)」と呼ばなければならない必然性(自然的根拠)はない
・記号は常に他律的な存在
→ 記号の認識は、他の記号との“差異”を通してのみおこなわれる
→ 例えば「学生」という記号の意味は、他のあらゆる「学生でないもの」との差異によってのみ認識される(記号Aの存在は、あらゆるnot Aの存在によってのみ保証される。下記を参照)
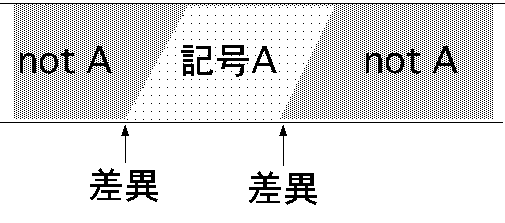
・世界から記号を見いだす働きを“分節(articulation)”と呼ぶ
→ 記号が見いだされる以前の世界は、モノやコトの区別の存在しない“連続体”(カオス)
→ “連続体”に分節線を引くことにより、記号が見いだされる
→ 分節とは、カオスに何らかの秩序を与える行為
→ 秩序は、文化的な構築物であるコードによって(のみ)与えられる(恣意性の原理2)
・コードとコンテクストの相補的関係
→ コードの拘束力は絶対的でない
→ コンテクストの介入によって、コードの与える分節線は変化する
→ 例えば「ありがとう」の意味は、発話のコンテクストによって異なる
・表現も意味も、読み取られてはじめて実在が許される
→ 分節のないところには表現も意味もない
・表現や意味の認定権(あるいは決定権)は、原理的に“読み手”の側にある
→ 「何が「表現」として認識されるか」「どのような意味が読み取られるか」は、読み手によって読み取られた通りでしかない
→ “表し手”の手を一旦離れたものは、原理的に制御不能
・“表すこと”は“伝えること”を保証されていない
→ 表現と伝達とは本質的には別々の行為
・従って、“この本の内容”はあらかじめ存在しない(形而上的存在としての「客観的意味」の否定)
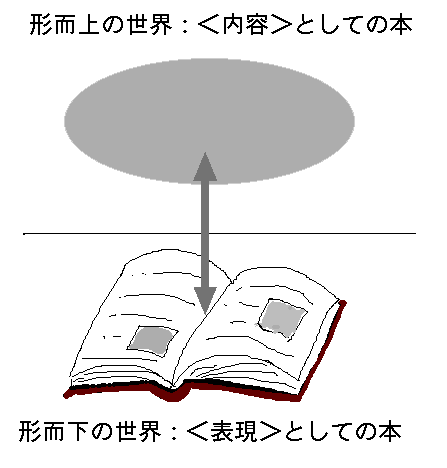
→ 「表現と意味(内容)の不可分性」は、「形而上(the physical)・形而下(the metaphysical)の絶対的な分化」を否定する
→ 従来の形而上学的認識・・・表現(形而下の存在)には、その本質的としての意味(内容・形而上の存在)が付随する
→ 表現すなわち意味は、読み手との関わりと無関係には存在しえない
・世界は記号(=意味)によって構成される
→ 人は分節を通してのみ世界を認識しうる
→ 私たちが認識しているのは、分節されたあとの世界
・分節の秩序(=コード)が、(認識される)世界のあり方を決める
→ コードの有り様によって、世界はいかようにでも姿を変える
→ 文化・習慣・世界認識の違いは、コード間の差異に還元される(例えば「先進文化と未開文化」といった対立の捉え直しに結びつく)
・コードを形成するのは、個々の具体的な分節の実践
→ 私たちの側が積極的に働きかけることにより、コードに変化がもたらされる可能性もある
→ ゆえに、私たちの意識的な実践によって、世界の姿が変化する可能性もある(例えば意図的、あるいは偶然的なコードの逸脱)
→ 分節の、世界に対する積極的な働きかけとしての側面を、特に「意味づけ」と呼ぶ
・人間の存在と無関係に意味(=情報)は存在しない
→ 意味は分節とともに生まれる
→ 例えば私たちとは無関係に「イヌ」は存在しない
→ 絶対的な意味での「客観的情報」は存在しない
・とにかく“言葉的なもの”として捉えられるあらゆる現象 は考察対象となりうる
<例1>「授業の選択」と情報
→ あとから振り返って、「授業の選択」に影響を与えた“情報”とはいったい何だったか
→ その“情報”を手に入れたとき、本当に“情報の収集”を意識していたのだろうか
→ 「情報収集」という観点から振り返った時に、見落とされたものはないだろうか(例えば授業のタイトルの記号性は?)
→ “慣習(あるいは「これまでのやり方」に基づく先入観、視野を限定する漠然とした要因)”はどれだけの影響力を持ちうるか
<例2>「テレビの視聴」と情報収集
→ テレビを見ているときに、「情報の収集」をどれだけ意識しているだろうか
→ 結果的に“情報”として役だったものは、どのような経緯で頭の中に入ってきたか
<例3>「メモを取る行為」と情報の生成
→ 「メモを取る行為」は一見すると情報の生成に結びつく
→ しかしながら、「メモとして取られたこと」は、無条件に“情報”たりうるか
→ 「メモを取る行為」自体の動機に、“情報”という要因はどれだけ関わっているか
<例4>「ホームページを出すこと」と情報の発信
→ 「ホームページを出すこと」は、情報の発信とどの程度関連するか
→ 「ホームページ」、「ホームページを持っている人」、「ホームページを持っていること」は、どのような記号性を有するか
→ 「ホームページを出すこと」が情報の発信に結びつくためには、どのような条件が必要か
・少なくとも、以下のことを学ぶことができる
→ 例えば“読む”という行為自体は、非常に慣習的(かつ無意識的)な側面を持っている
→ また、その際の私たちの視野は自ずとコードによって限定されている
→ そのような“読む”という行為と、“情報の収集”との間に、本質的な境界線は引けない
→ 従って、その境界線は、私たちが意図的に引いてゆかねばならない
・また、情報発信を試みる際に考えるべきこととして、以下のことを学ぶことができる
・これらを通して、逆に、“情報とは何か”についてを問い返す契機となる
→ “情報”を出発点(前提)としない情報教育
→ 学習者自らが“情報とは何か”についてを考える(考えざるを得ない)